
ビジネスシーンや特別な日に足元を引き締めてくれる大切な革靴。しかし、いざという時に不快な匂いがして、困惑した経験はありませんか。
革靴の匂い消しで最強の方法を求めて情報を探しているものの、靴消臭アイテムをドラッグストアで探したり、入れるだけの便利な商品を試したりと、その選択肢は多岐にわたります。
また、昔ながらの知恵として靴の匂い消しに重曹や10円玉が良いという話を聞いたことがあるかもしれません。
あるいは、手軽さから衣類用のファブリーズで代用できないかと考えたり、最終手段としての洗い方を検討したりと、様々な情報が溢れています。会食の席など、急な場面で靴の臭いを一瞬で消す方法も、社会人としてのマナーとして知っておきたいところです。
この記事では、そんなあなたの尽きない悩みを根本から解決するために、科学的根拠に基づいた効果的な対策から、今日からすぐに試せる手軽な裏技まで、革靴の匂いを断つための知識と具体的な方法を、より深く、そして徹底的に解説していきます。
この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。
革靴の匂い消し最強への道【原因と対策】
- そもそも革靴の匂いを消す方法はありますか?
- 靴が臭すぎる時はどうすればいいですか?
- 緊急時に靴の臭いを一瞬で消す方法
- 靴消臭ドラッグストアで探す匂い消し
- 手軽な靴消臭は入れるだけのタイプが人気
- 革靴にファブリーズを使う時の注意点
そもそも革靴の匂いを消す方法はありますか?

はい、革靴の匂いを効果的に消す方法は確かに存在します。しかし、そのためには表面的な対処療法に終始するのではなく、なぜ匂いが発生するのか、そのメカニズムを正しく理解することが何よりも大切になります。
革靴から発生する不快な匂いの主な原因は、私たちの足から分泌される汗や皮脂、そして新陳代謝によって剥がれ落ちた古い角質です。
これらが靴の中に溜まり、そこに元々存在している皮膚常在菌(表皮ブドウ球菌など)のエサとなります。
菌はこれらのエサを分解する過程で、特定の揮発性ガスを発生させます。その代表格が「イソ吉草酸(いそきちそうさん)」と呼ばれる物質で、これがあの納豆やむれた靴下を連想させる、強烈な悪臭の正体なのです。
特に革靴は、一般的なスニーカーなどの布製の靴と比較して、素材の特性や構造上、通気性が悪いものが少なくありません。
そのため、靴の内部は高温多湿な環境、いわば「雑菌の培養器」のような状態になりがちです。この環境は雑菌の繁殖を飛躍的に加速させる大きな要因となります。
さらに、革という素材自体が湿気を吸収しやすい性質を持つため、一度汗などで湿ってしまうと内部が乾きにくく、匂いが定着しやすいという側面も持ち合わせています。
【ポイント】革靴の匂い対策 3つのアプローチ
したがって、革靴の匂いを根本的に解決するためには、ただ香りの良いスプレーで匂いを上から覆いかぶせる「マスキング」ではなく、以下の3つのアプローチを組み合わせることが鍵となります。
- 乾燥: 雑菌の繁殖に不可欠な「湿気」を取り除き、菌が活動しにくい環境を作る。
- 除菌・抗菌: 匂いを発生させる元凶である「雑菌」そのものを除去、または繁殖を抑制する。
- 吸着・中和: すでに発生してしまった「匂い成分」を物理的・化学的に取り除く。
これらのアプローチを理解し、状況に応じて適切なケアを実践することで、大切な革靴を匂いの悩みから解放することが可能になります。
靴が臭すぎる時はどうすればいいですか?

靴の匂いが「臭すぎる」と感じるレベルにまで達してしまった場合、単一の対策では効果が薄いことがほとんどです。このような深刻な状況では、複数のアプローチを組み合わせた複合的な対策が必要不可欠となります。
まず、全ての対策の基本であり、最も重要なのが「靴を徹底的に乾燥させる」ことです。
一度履いた革靴は、目には見えなくても内部にかなりの湿気を含んでいます。同じ靴を毎日連続で履くのは、雑菌にエサと快適な住処を与え続けているようなものです。
最低でも2足をローテーションし、履いた靴は1日以上休ませるのが理想ですが、匂いが強い場合は3足以上でローテーションを組み、2日以上は間隔をあけてください。保管場所は、風通しの良い日陰が最適です。
シューキーパー(シューツリー)の活用を習慣に
靴を休ませる際には、木製のシューキーパー(特に吸湿性に優れたシダー製がおすすめ)を入れておくことを強く推奨します。
シューキーパーは、靴の履きジワを伸ばして型崩れを防ぐだけでなく、内部の湿気を効果的に吸収し、乾燥を促進する重要な役割を果たします。プラスチック製のものに比べて高価ですが、その効果は絶大です。
次に、日常的なケアに加えて、市販の消臭・除菌グッズを積極的に活用します。匂いが特にひどい場合は、まず即効性のある除菌・消臭スプレーを靴内部にしっかりと噴霧し、雑菌の活動を抑制します。
その後、竹炭や活性炭、珪藻土など、匂いを強力に吸着するタイプの置き型脱臭剤を靴の中に入れて一晩置きます。この「スプレーで攻撃し、置き型で吸収する」という二段階の対策は、多くの場合で匂いを劇的に軽減させることが可能です。
これらの対策を講じてもなお匂いが改善されない場合、それは靴の内部、特にインソールやライニング(内張り)の繊維の奥深くに、長年の汗や皮脂汚れが蓄積し、雑菌の巨大な温床(バイオフィルム)が形成されてしまっている可能性が高いです。
この段階になると、表面的なケアでは限界があります。最終手段として、革靴専門のクリーニングサービスに依頼することを検討しましょう。
専門家は素材を傷めない特殊な洗剤と技術で内部まで丸洗いしてくれるため、汚れごと匂いの原因を根本から除去し、見違えるほどリフレッシュさせることが期待できます。
緊急時に靴の臭いを一瞬で消す方法

重要な会食や知人宅への訪問など、予期せぬタイミングで靴を脱がなければならない場面は、誰にでも訪れる可能性があります。「今すぐ、この匂いをどうにかしたい!」という切迫した状況では、即効性のある応急処置が求められます。
最も手軽かつ効果的な方法は、携帯用に販売されている靴専用の消臭スプレーを活用することです。
最近ではドラッグストアやコンビニエンスストアなどで、カバンに入れても邪魔にならないコンパクトな製品が多数販売されています。選ぶ際のポイントは、除菌・抗菌成分(銀イオンなど)が明記されているものを選ぶこと。
これにより、匂いを香りで上書きするだけでなく、原因菌に直接アプローチできます。スプレーする際は、靴の中全体、特に汗が溜まりやすいインソールと、雑菌が最も繁殖しやすい「つま先」部分にしっかりと行き渡るように数回プッシュするのがコツです。
すぐに靴を履くことを想定し、噴射後にサラサラになる速乾性の高いパウダースプレータイプを選ぶと、足を入れた時の不快な湿り気がなく快適です。
もしスプレーが手元にないという絶体絶命の状況であれば、アルコール成分が含まれた除菌ウェットティッシュが代役を果たしてくれます。
ティッシュで靴の内側、特に足が直接触れるインソールの表面を丁寧に拭き取ります。アルコールには殺菌作用と高い揮発性があるため、原因菌の数を一時的に減らしつつ、気化したアルコールと共に匂い成分をある程度飛ばす効果が期待できます。
【緊急時対応の注意点】
- アルコールの使用: 革に直接アルコールが大量に付着すると、シミや変質、色落ちの原因となる可能性があります。あくまでインソールや内側の布地部分など、革ではない部分への使用に限定し、優しく拭く程度に留めてください。
- あくまで応急処置: これらの方法は、その場を乗り切るための一時的な対策です。匂いの根本的な解決にはならないため、帰宅後には必ず前述したような本格的なケアを行うことが重要です。
これらの緊急対策を知っておくだけで、いざという時の精神的な安心感に繋がります。
靴消臭ドラッグストアで探す匂い消し

ドラッグストアは、まさに靴の匂い対策グッズの宝庫です。多種多様な製品が所狭しと棚に並んでおり、それぞれの特性を正しく理解して選ぶことで、ご自身のライフスタイルや匂いのレベルに最適なアイテムを見つけ出すことができます。
ドラッグストアで手に入る製品は、主に以下の4つのタイプに大別されます。それぞれのメリット・デメリットを把握し、賢く選びましょう。
| 種類 | 主な特徴とメリット | デメリット・注意点 | こんな人におすすめ |
| スプレータイプ | ・即効性が非常に高い ・外出前や気になった時にすぐ使える ・除菌・抗菌成分配合の製品が豊富 | ・効果の持続時間は製品により差がある ・革の表面に直接かかるとシミになる可能性 ・ガス抜きなど廃棄に手間がかかる場合がある | ・外出先で急に匂いが気になる人 ・即効性を最優先したい人 |
| パウダータイプ | ・靴内部の湿気を強力に吸収する ・サラサラな状態を保ち、菌の繁殖を抑制 ・一度の使用で効果が比較的長く持続する | ・粉が靴下やストッキングに付着しやすい ・靴を脱いだ際に粉が目立つことがある ・入れる量の調整に少しコツがいる | ・足汗をかきやすい人 ・持続性を重視する人 |
| 置き型タイプ | ・靴の中に入れておくだけで非常に手軽 ・竹炭、活性炭、珪藻土など自然素材が多い ・繰り返し使えるものが多く経済的 | ・スプレーに比べて即効性は低い ・効果を発揮するのに数時間~一晩かかる ・定期的な交換や天日干しなどの手入れが必要 | ・毎日のケアを習慣化したい人 ・手間をかけたくない人 |
| インソールタイプ | ・消臭・抗菌機能を持つ中敷き ・歩きながら継続的に匂い対策ができる ・クッション性を兼ね備えた製品もある | ・靴のサイズ感(フィット感)が変わる可能性 ・効果が薄れたら定期的な交換が必要 ・費用が比較的高くなる傾向がある | ・長時間革靴を履き続ける人 ・足の疲れも同時にケアしたい人 |
製品選びの鍵は「成分表示」の確認
タイプを選んだら、次に注目すべきは成分表示です。
匂いの原因菌に対して高い効果を発揮する「銀イオン(Ag+)」や、優れた除菌効果を持つ「イソプロピルメチルフェノール」、天然由来の消臭・収れん成分である「ミョウバン(焼ミョウバン)」などが含まれている製品は、信頼性が高いと言えます。
また、香りでごまかすタイプの製品は、革靴の酸っぱい匂いと混ざって、さらに不快な化学的悪臭に変化することがあります。可能な限り「無香料」タイプを選ぶのが、最も安全で確実な選択です。
まずはご自身のライフスタイル(すぐに匂いを消したいのか、手間をかけずに継続したいのかなど)に合わせてタイプを絞り込み、次に成分を確認するという手順で探すことで、数多くの製品の中から最適な一つを見つけやすくなるでしょう。
手軽な靴消臭は入れるだけのタイプが人気

日々の多忙なスケジュールの中で、「手間をかけずに、でも確実に靴の匂い対策をしたい」と考える方々から絶大な支持を得ているのが、「入れるだけ」でケアが完了する置き型の消臭・除湿剤です。
このタイプの最大の魅力は、その圧倒的な手軽さにあります。一日の終わりに帰宅して靴を脱いだ後、製品をポンと中に入れておくだけ。
あとは寝ている間や、靴を休ませている間に、有効成分が自動的に消臭と除湿を進めてくれます。
スプレーのように毎回噴射する手間もなければ、パウダーのように粉が周囲に飛び散る心配も一切ありません。この「手間ゼロ」感覚が、継続的なケアを可能にし、結果的にクリーンな靴内環境を維持することに繋がるのです。
素材には様々な種類があり、それぞれにユニークな特徴がありますので、ニーズに合わせて選ぶと良いでしょう。
- 竹炭・備長炭: 日本で古くから利用されてきた、信頼性の高い脱臭素材です。木炭を高温で焼成する過程で、内部に無数の微細な孔(あな)が形成されます。この孔が匂いの原因物質や湿気の分子を物理的に吸着する「多孔質構造」を持っており、強力な脱臭・除湿効果を発揮します。化学物質を使用しないため、安全性が高い点も魅力です。
- 珪藻土(けいそうど): 太古の植物性プランクトン(珪藻)の化石が堆積してできた土です。竹炭同様、目に見えない無数の孔を持ち、特に吸湿能力が非常に高いことで知られています。靴の中の湿気を素早く吸収し、雑菌が繁殖しにくいカラッとした環境を作り出すことで、匂いの発生を元から抑制します。バスマットなどにも利用される、注目の自然素材です。
- シダー(杉): シューキーパーの素材としても最高級とされる天然の木材です。湿気を吸収・放出する「調湿効果」に優れているだけでなく、シダー自体が持つフィトンチッドという成分により、爽やかな木の香りが靴内をリフレッシュさせ、消臭・防虫・抗菌効果を発揮します。機能性と心地よい香りを両立させたい方におすすめです。
多くの製品が、月に一度程度の天日干しをすることで吸湿・脱臭能力が回復し、半年から1年以上繰り返し使用できるため、コストパフォーマンスに優れている点も人気の大きな理由です。
一方で、デメリットとして繰り返しになりますが、スプレータイプと比較して即効性に劣る点が挙げられます。
入れてすぐに匂いが完全に消えるわけではなく、数時間から一晩という時間をかけてじっくりと効果を発揮するものがほとんどです。
したがって、外出前の緊急対策というよりは、日々のルーティンとして取り入れ、匂いを「予防する」「蓄積させない」ための、守りのケアとして最適な方法と言えるでしょう。
革靴にファブリーズを使う時の注意点

家庭用の布製品消臭スプレーとして絶大な知名度を誇るファブリーズ。「これを革靴の匂い消しにも使えないか?」と考えるのは自然な発想かもしれません。
しかし、結論から申し上げると、革靴、特にその表面(アッパー)にファブリーズを直接吹きかけることは、重大なダメージを引き起こす可能性があるため、絶対に避けるべきです。
その最大の理由は、ファブリーズの主成分が「水分」であり、革製品との相性が極めて悪いことにあります。天然素材である革は、水分を急激に吸収すると次のようなトラブルを引き起こすリスクがあります。
- シミ: 水分が浸透した部分だけ色が濃くなり、乾いても元に戻らない「水ジミ」が発生する可能性があります。
- 硬化・ひび割れ: 革に含まれている油分が水分と一緒に揮発してしまい、革が柔軟性を失って硬くなり、最終的には表面にひび割れ(クラック)が生じることがあります。
- カビの発生: スプレーによって与えられた水分が完全に乾ききらないと、かえってカビの発生を助長する温床になりかねません。
また、ファブリーズに含まれる香料が、革靴特有の汗や皮脂が酸化した匂いと混ざり合うことで、想像以上に不快な、化学的な悪臭へと変化してしまう「匂いのミスマッチ」も懸念されます。
革靴などにファブリーズ等を限定的に使用する方法(非推奨)
注意: 他の手段がなく、自己責任の上で使用する場合の限定的な手順です。
- 革への直接噴霧は厳禁:革の部分には絶対にスプレーしない。
- 対象は内側の布地のみ:靴の内側の布地(ライニング)や布製インソールに限定して使用する。
- 「間接塗布」を徹底:
- 乾いた清潔な布に1〜2回軽くスプレーする。
- その布で、こすらずに優しく叩くようにして内側の布地部分に成分を付着させる。
- パッチテストは必須:本格的に使う前に、かかとの内側など目立たない部分で試し、シミや変色が起きないことを必ず確認する。
このように、ファブリーズを革靴に使用するには多大なリスクと細心の注意が伴います。安全かつ効果的に大切な革靴をケアするためには、やはり革靴専用に成分が調整・開発された消臭・除菌スプレーを使用することが、最も賢明で後悔のない選択です。
身近な物で実践!革靴の匂い消し最強テク
- 靴の匂い消しに重曹!一晩つけるとどうなる?
- 革靴に10円玉を入れるとどうなる?その効果
- 根本から解決する革靴の正しい洗い方
靴の匂い消しに重曹!一晩つけるとどうなる?

キッチン周りの掃除や料理のあく抜きなど、家庭の様々な場面で「万能パウダー」として活躍する重曹は、実は靴の匂い消しとしても驚くほど高い効果を発揮するアイテムです。化学的な性質を利用したこの方法は、コストをかけずに実践できる優れた対策の一つと言えます。
重曹の正式名称は「炭酸水素ナトリウム」であり、その性質は「弱アルカリ性」です。
一方で、繰り返しになりますが、靴の悪臭の主犯格である「イソ吉草酸」は「酸性」の物質です。理科の授業で習ったように、アルカリ性の物質と酸性の物質が出会うと「中和反応」が起こります。
つまり、靴の中に弱アルカリ性の重曹を置くことで、酸性の匂い成分が化学的に中和され、無臭の物質に変化するのです。これは、香りで匂いを上から覆い隠すマスキングとは全く異なる、匂いの元を断つ科学的なアプローチです。
さらに、重曹の微細な粉末には、湿気を吸収する「吸湿性」もあります。靴の中のジメジメとした不快な湿気を取り除くことで、匂いの原因となる雑菌が繁殖しにくい乾燥した環境を作り出します。
これにより、匂いの除去(消臭)と、匂いの再発予防(防臭)の両方に貢献してくれるのです。
具体的な使い方は驚くほど簡単で、誰でもすぐに実践できます。
【重曹消臭袋の作り方と使い方】
- 準備: 通気性の良い小袋を用意します。市販のお茶パックやだしパックが最適ですが、なければ古い靴下やストッキングの切れ端などでも代用可能です。
- 封入: 用意した袋に、重曹(食用グレードでも掃除用グレードでも可)を大さじ3〜4杯程度入れます。量が多すぎると靴に入れにくくなるので、靴のサイズに合わせて調整してください。
- 密封: 袋の口を輪ゴムや紐でしっかりと縛り、中の粉が絶対に漏れ出ないようにします。
- 設置: 完成した重曹消臭袋を、革靴の中に片足ずつ入れて、一晩(約8時間以上)そのまま放置します。
- 交換: 2〜3ヶ月を目安に、中の重曹が湿気を吸って固まってきたら新しいものと交換しましょう。
この方法の最大のメリットは、何と言ってもコストパフォーマンスの高さと、食品添加物としても使われる成分ならではの安全性の高さです。
ただし、注意点として、重曹のアルカリ性の粉末が革に直接長時間付着すると、革の油分を過剰に奪って乾燥や硬化を招いたり、鞣し(なめし)の成分と反応してシミの原因になったりする可能性があります。
そのため、必ず袋に入れて使用し、粉がこぼれ出ないように細心の注意を払ってください。
革靴に10円玉を入れるとどうなる?その効果

「靴の中に10円玉を数枚入れておくと匂いが消える」という話は、祖母の知恵袋のような形で古くから語り継がれてきた、有名な生活の裏技の一つです。一見すると迷信のようにも聞こえますが、実はこの方法には科学的な根拠が部分的に存在します。
日本の10円硬貨は、その約95%が「銅」で構成されています。この銅という金属は、水分と反応すると微量の「銅イオン」を放出する性質があります。
そして、この銅イオンには、細菌などの微生物の細胞膜に作用してその活動を阻害する、いわゆる「殺菌・抗菌作用」があることが科学的に証明されています。
靴の匂いの根本原因が雑菌の繁殖にあることを考えれば、銅イオンの力によってその繁殖を抑えることができれば、結果的に匂いの発生を抑制できる、という理屈が成り立ちます。
実際に、この銅イオンの優れた殺菌効果は、靴の中敷き(インソール)や抗菌加工の靴下、キッチンの排水溝のぬめり取りなど、私たちの身の回りの様々な製品に応用されています。したがって、革靴の中に10円玉を入れておくことにも、一定の効果は期待できると言えるでしょう。
しかし、この方法の効果にはいくつかの限界があることも、冷静に理解しておく必要があります。
- 効果の範囲の限定性: 10円玉から放出される銅イオンの効果は、硬貨が直接接触している部分やそのごく周辺に限られます。靴全体の広範囲にわたる雑菌を抑制するほどのパワーはありません。
- 即効性の欠如: 銅イオンがゆっくりと作用するため、すでについてしまった強い匂いを瞬時に消し去るほどの即効性は期待できません。効果を実感するには時間がかかります。
- 衛生面の問題: 流通している硬貨は非常に多くの人の手に触れており、汚れています。汚れた10円玉をそのまま入れると、かえって靴の中を汚してしまう可能性があります。もし試す場合は、一度きれいに洗浄・乾燥させた硬貨を使用しましょう。
これらの点を総合的に考慮すると、10円玉を入れる方法は、あくまで匂いを「予防」するための補助的な、あるいは気休めに近い手段と捉えるのが適切です。
これ単体で匂い問題を解決しようとするのではなく、他の消臭対策と組み合わせることで、よりクリーンな靴内環境を維持する一助になるかもしれない、という程度の認識でいるのが良いでしょう。
根本から解決する革靴の正しい洗い方
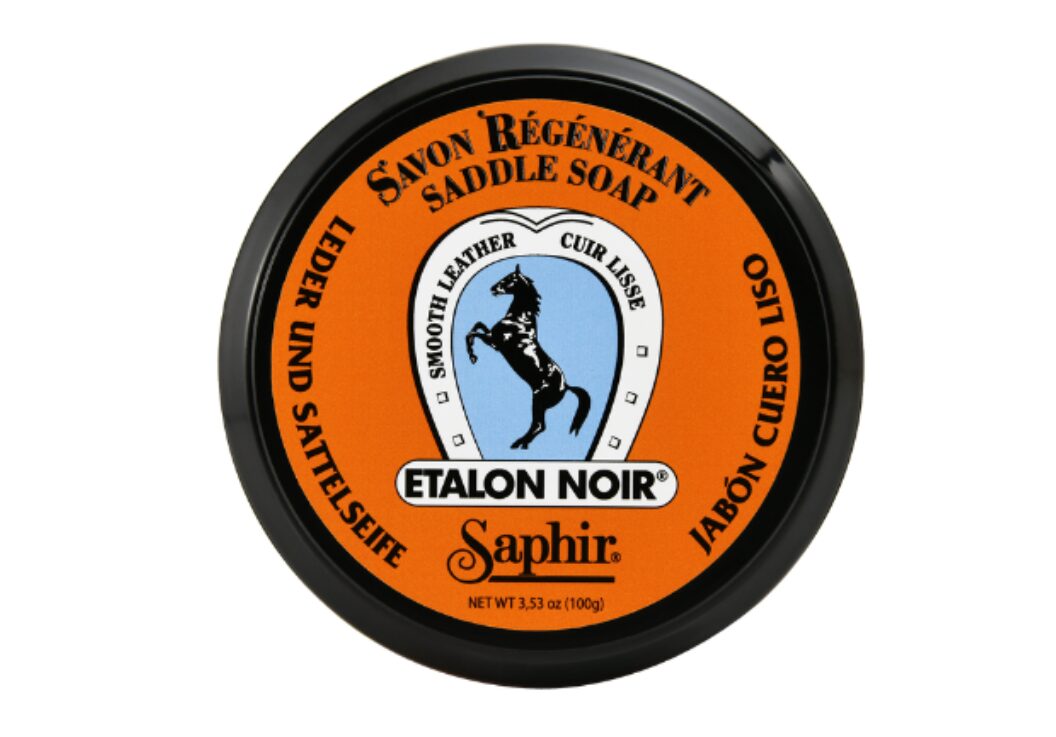
革靴に染み込んだ長年の汗や汚れが原因で、どのような消臭対策を施しても匂いが取れない——。
そのような末期的な状況に陥った場合の最終手段として「革靴を洗う」という選択肢がありますが、これは「諸刃の剣」であることをまず強く認識してください。革は水に非常に弱く、洗浄には専門的な知識と繊細な技術が要求されます。
最も安全で確実、そして推奨される方法は、迷わず革靴専門のクリーニング店や腕の良い靴修理店に依頼することです。
プロフェッショナルは、革の種類(カーフ、キップ、ステアなど)、鞣し方(クロム鞣し、タンニン鞣しなど)、製法(グッドイヤーウェルト、マッケイなど)を正確に見極め、それぞれの靴に最適な専用の洗剤や道具を用いて、洗浄から栄養補給、乾燥、仕上げまでの全工程を完璧に行ってくれます。
料金はかかりますが、大切な一足をダメにしてしまうリスクを考えれば、決して高い投資ではありません。
もし、それでもなお自宅で洗うことに挑戦する場合は、最悪の場合その靴を諦める覚悟を持った上で、自己責任で行う必要があります。
特に、スエードやヌバックといった起毛革、エナメルやコードバンなどの特殊な加工が施された革は非常にデリケートなため、自宅での洗浄は絶対に避けるべきです。
以下に、一般的なスムースレザー(表面が滑らかな革)を対象とした洗浄手順の一例を詳しく紹介しますが、これはあくまで参考情報であり、成功を保証するものではないことをご了承ください。
自宅で革靴を洗う手順(ハイリスク)
■ 準備するもの
- 革靴専用シャンプー(サドルソープなど)
- 馬毛ブラシ(ホコリ落とし用)
- 靴用ブラシ(洗浄用、硬いものは不可)
- スポンジ(複数)
- 吸水性の高い乾いた布(複数枚)
- 木製のシューキーパー
■ 洗浄手順
- 下準備
- 靴紐を外す。
- 馬毛ブラシで、縫い目を含め靴全体のホコリや泥汚れを優しく払い落とす。
- 全体を濡らす
- 水を含ませたスポンジで、表面全体を均一に湿らせる。
- 重要:水ジミを防ぐため、必ずムラなく全体がしっとりするまで濡らす。
- シャンプーで洗う
- 湿らせた洗浄用ブラシにシャンプーをつけ、円を描くように優しく泡立てながら洗う。
- 内側やインソールも、指や柔らかいブラシで念入りに洗浄する。
- 泡の拭き取り(すすぎ)
- 水で直接洗い流さず、新しいスポンジや固く絞った布で泡を何度も丁寧に拭き取る。
- 泡が完全に見えなくなるまで繰り返す。
- 水分除去と乾燥
- 乾いた布で全体の水分を押し当てるように吸い取る。
- すぐに木製のシューキーパーを入れて形を整える。
- 重要:直射日光やドライヤーは避け、風通しの良い日陰で数日間(3日〜1週間程度)かけて自然乾燥させる。
- 保湿・栄養補給ケア
- 完全に乾いたら、デリケートクリームやシュークリームを薄く均一に塗り込み、油分と潤いを補給する。
- 注意:この工程を怠ると、革が硬くなったり、ひび割れたりする原因になる。
ご覧の通り、このプロセスには多大な時間と手間、そして細心の注意が必要です。
一つでも手順を誤ると、修復不可能なダメージを与えてしまう可能性があります。重ねて申し上げますが、大切な革靴を長く愛用するためには、プロの手に委ねることが最善の策です。
まとめ:あなたに合う革靴の匂い消し最強法
- 革靴の不快な匂いの主な原因は雑菌の繁殖とその代謝物
- 匂いの元となる主成分はイソ吉草酸という酸性の物質
- 通気性の悪い革靴は高温多湿になりやすく雑菌の温床となりがち
- 基本の対策は同じ靴を毎日履き続けずローテーションさせること
- 履いた後は必ず風通しの良い日陰で内部までしっかり乾燥させる
- 木製のシューキーパーは湿気取りと型崩れ防止に絶大な効果を発揮
- 即効性を求めるなら除菌・抗菌成分が含まれた靴専用消臭スプレーが最適
- ドラッグストアではスプレー、パウダー、置き型、インソールなど多様なグッズが手に入る
- 日々の手軽な継続ケアには靴の中に入れるだけの置き型消臭剤が便利で人気
- 竹炭や珪藻土などの自然素材は吸湿と脱臭の両方に優れた効果を発揮
- 家庭にある身近なアイテムでは弱アルカリ性の重曹が酸性の匂いを中和するのに役立つ
- 重曹を使用する際は革に直接粉が触れないよう必ず布袋に入れること
- 10円玉の銅イオンには限定的ながら殺菌効果が期待できるが補助的な手段と心得る
- 衣類用のファブリーズを革靴の革部分に直接スプレーするのは絶対NG
- あらゆる対策を尽くしても匂いが取れない場合の最終手段は専門業者によるクリーニング
- 自分にとっての最強の対策法とは、一つの方法に固執せず、乾燥・除菌・吸着といったアプローチを日々のケアの中にバランス良く取り入れること
参考記事